4. 新生ラスプーチン
皇帝は1905年11月1日の日記に「ミリツァとスタナとお茶を飲んだ」と書いている。「トボリスク州から来た神の人、グレゴリーと知り合いになった。」ニコライとアレクサンドラは、ラスプーチンとペテルホフにあるモンテネグロ人の優雅な別荘、セルゲイエフカで会ったばかりだった。皇帝夫妻は、出会ったばかりの男と驚くべき友情を築くことになるとは思いもよらなかったし、彼が自分たちの破滅に大きな役割を果たすことになるとも思いもしなかった。
会談が実現するまでには2年の歳月を要した。1903年、フェオファンがモンテネグロの姉妹にラスプーチンを紹介したとき、農夫はこの重要人物を使って皇帝とその家族に会いたいと思ったのである。姉妹はその時期が来たとは思っていなかった。フィリップ・ナジエ・ヴァショ博士がまだ活躍していたため、ニコライとアレクサンドラはフランス人の訪問者に与えていたような注目を新しい男性(ラスプーチンのような)に注ぐことはないだろうと考えていた。しかし、2年後の1905年にラスプーチンが首都に戻ったとき、フィリップはいなかった。(アナスタシアとミリツァは、アレクサンドラがナジエ・ヴァショとの関係の終わり方に落ち込んでいることを知っていたので、ラスプーチンを登場させるタイミングだと思われた。1905年の秋、華やかな午後の4時、ニコラィとアレクサンドラは「トボルスク州から来た神の人」に会う準備をした。
アナスタシアとミリツァがラスプーチンを推したのは、確かに世俗的な動機があった。彼らは、ラスプーチンが恩義を感じて従順になり、皇室に賛美を送り、ツァールスコエ・セローの刻々と変化する政治情勢について有益な情報を伝えてくれると思い込んでいた。この姉妹には理想主義的なところもあった。宗教的な情熱もあり、新しい友人をアレクサンドラに紹介することを切望していた。ラスプーチンは旧約聖書の預言者のような存在であった。姉妹は彼の福音書、特に黙示録の解説が “突き刺すようで独創的 “であると感じた。 ラスプーチンは病気を治し、未来を予言し、 不幸を取り除くことができると断言した。彼らは、長い間求めていた “奇跡の人 “をついに見つけることができたと感激した。
また彼らは、ラスプーチンをコントロールすることにも頭を悩ませていた。彼は単純な男だから、自分で操作しようとすると墜落してしまうとラスプーチンに説明した。皇室と接触するようなことは、決してしてはならないのだ。ラスプーチンはこのゲームに苦笑したに違いない。ラスプーチンが狡猾で策略家であることを見抜けなかったのだ。最後に、彼がすべてを逆転させるだろうことも。
ラスプーチンは実際に皇帝に会ったとき、勝利の瞬間を味わったに違いないが、グレゴリーは全くリラックスして自信に満ちていた。彼は皇帝夫妻を「バチューシカ」「マチューシカ」(「小さな父上」「小さな母上」)と呼んだ。農民が君主とその配偶者を呼ぶときに使う名前であった。ラスプーチンは二人と話すとき、身分の高い人を指す「vy」ではなく、ロシア人が家族や友人に使う「あなた」の形である「ty」を使った。ニコライとアレクサンドラは、堅苦しい人や不誠実な人を嫌っていたので、このようなカジュアルさをすぐに気に入ったのだろう。
ニコライとアレクサンドラがラスプーチンに再会するまで8カ月が過ぎた。彼はポクロブスコエで冬を過ごしたようだ。彼は首都に戻ると電報を打ち、「皇帝陛下。シベリアからこの都市に到着した私は、奇跡の労働者であるヴェルコチューリエの聖なる抱神者シメオンの聖像を持ってきたいと思います “と告げた。1906年7月18日、皇帝夫妻はラスプーチンをお茶に招いた。
会見はうまくいったのだろう。1906年10月12日(金)、ラスプーチンは再び宮殿に招かれることになった。ニコライとアレクサンドラは、「ロシア国民の声」を聞きたいと常に考えていた。ラスプーチンは彼らの期待を満足させるに十分な抜け目なさを備えていた。実際、この訪問が彼の転機となったようで、お茶の後、ラスプーチンは皇帝の娘たちとその2歳の弟アレクシスに紹介された。ニコライ2世の日記には、この頃息子が体調を崩し、落ち着きがなかったことが記されている。
娘マリア・ラスプーチンは、1906年に初めて父がアレクシスの健康を祈願したと考えていた。もしそうなら、10月12日がその日だったのかもしれない。4日後の1906年10月16日、ニコライはラスプーチンを、ピーター・ストリピンに最近降りかかった問題に巻き込んでしまったからである。1906年8月、首相官邸の夏の別荘が爆弾テロによって破壊され、32人が死亡、14歳の娘ナターリヤも重軽傷を負った。ラスプーチンが最近家族を訪れ、「女王陛下と私の両方に強い印象を与えたので、彼との会話は5分ではなく1時間以上続いた」と記したメモを皇帝はストリピンに書き送った。皇帝は、この農夫は治癒の才能があるので、ナターリヤを訪ねて彼女のために祈ることは有益であろうと説明した。ストリピンはその場におらず、治療も行われなかったが、要求通りにした。
10月12日、ラスプーチンがアレクサンドル宮殿を去るとき、皇帝は側近のプチャーチン王子に、この訪問者についての感想を求めた。プチャーチンは、「この農民は不誠実で情緒不安定だ」と答えた。ニコライはプチャーチンを素っ気なくうなずいて退け、それ以来、彼にラスプーチンのことを口にすることはなかった。
この訪問の直後、皇后の侍女の一人であったエリザベス・ナリーシキナ=クラキナ王女は、このときからアレクサンドル宮殿で「ラスプーチン」の名を耳にするようになったと回想している。このことは、ラスプーチンがツァレーヴィチ(皇子)の健康を祈るように言われたのは、10月12日の会議が初めてだったという説に重みを与えている。ラスプーチンはただの放浪の巡礼者と奇跡を起こす人を区別する境界線を越えていたのだ。1906年12月9日、皇帝は「ミリツァとスタナと食事をした」と記している。”我々は夜通しグレゴリーについて話した”。
6日後の12月15日、今度はラスプーチンがニコライに頼みごとをする番だった。自分の名前を合法的に修正するよう、皇帝に請願したのである。ポクロブスコエの6つの家族がラスプーチン姓を名乗っており、これが「あらゆる種類の混乱」を引き起こしていると説明した。ラスプーチンはニコライに「私と子孫がラスプーチン=ノヴィーという名前を名乗ることを許可し、この混乱を終わらせるように」と頼んだ。ラスプーチン=ノヴィーとは新ラスプチンという意味である。ニコライはこの要求を承認しただけでなく、嘆願書に「陛下は彼のこの特別な要求を許可する」と記した。1906年12月22日付の勅令で、この変更は承認された。ロシアは官僚主義で有名だが、7日間というのは、どう考えてもスピードが速い。皇帝がこの問題に注目したことは、1906年12月までにラスプーチンを特別視するようになったことを示唆している。
ラスプーチンの依頼は、彼の家が苗字がないほど貧しいという噂に端を発したものだろう。村人たちは、彼の浪費癖からラスプーチンと名付けたとされる。ラスプーチンの名前の由来が「酔っぱらうこと、放蕩すること」であるという考え方は伝説となり、彼の支持者を悩ませていた。ニコライとアレクサンドラはこの農民を「グレゴリー」または「我々の友人」と呼んだが、決して「ラスプーチン」とは呼ばなかった。アレクサンドラは夫に宛てた手紙の中で、共通の知人が古い姓を使っていることに不満を漏らしたことがある。皇后は自分の主張を伝えるために “ラスプー”と書いた。ということは、この名前を最後まで書く気になれないほど、嫌な名前だと思ったのかもしれない。「私はそれが好きではない」と、彼女は友人に書いている。
「ノヴィー」あるいは「ノヴィーク」という名前をつけることを許可してほしいと頼んだのはラスプーチンだったが、彼はそれが自分の考えだとは認めようとしない。ラスプーチンは、初めて皇帝の子供部屋に入ったとき、アレクシスはベビーベッドの上で飛び跳ねて、”新しい!”と叫んだと主張した。これは事実ではなく、ラスプーチンは他にも矛盾する嘘をつくのが常であった。時には、ニコラスが勝手にノヴィーと名付けたと自慢することもあった。このことを証明するかのように、ラスプーチンは自分のパスポートを広げて、それが確かに “ラスプーチン=ノヴィー “であることを示すのである。ノヴィーはロシア人の名前ではないし、それを名乗るような男は、自分の過去や伝統を破っているように見えるだろう。1906年、ラスプーチンは新しい環境で新しい人に会い、新しい経験を味わっていた。彼は過去ではなく、現在に基づいた新しいアイデンティティを築くことを切望していた。
ラスプーチンは1907年4月6日と6月19日に再び宮殿を訪れた。そのうちの1回、おそらく6月19日、彼はアレクシスがひどく苦しんでいるのを見た。皇帝の妹のオルガは、甥が倒れて内出血を起こしたと回想している。「数時間のうちに、子供は耐え難い痛みに襲われた」。医者もお手上げだった。その夜遅く、アレクサンドラはラスプーチンを呼び寄せた。翌朝、オルガは甥が元気であることを確認した。アレクサンドラは、ラスプーチンが夜に来て息子のために祈ったと語った。
アレクサンドラは、神がラスプーチンを送り込んだと信じていた。彼女は祈りの力を確信していた。ある侍女が、両親が薬ではなく、祈りで病気を治したために、ある子供たちが死んだという報道を見て、怒りをあらわにしたことがある。「祈りが足りなかったのです!」 アレクサンドラは答えた。「両親が熱心に祈っていれば、子どもたちは回復していたでしょう」と。
アレクサンドラが息子のために祈り続けても、なかなか結果が出なかったことを思えば、これは悲しい意見である。息子の悲劇は、自分の罪に対する罰なのではないかとも考えたようだ。エリザベス・ナリーシキナ=クラキナ王女は、ラスプーチンがこの繊細な感情を利用してゆすりを行っていたと考えた。彼が「彼女の罪悪感を強調することによって皇后に影響を与えた」と主張していた。おそらくラスプーチンは賢く、直接的にそれを行うことはなかったのだろう。 もしこの話題が出たら、彼は皇后に息子の不幸は神の裁きではないと断言し、どんな懸念が残ろうと自分に有利に働くことを知っていたのだろう。それよりも、ニコライとアレクサンドラには、彼がいる限り息子の生活は安泰だと思わせる方が賢明であっただろう。もし、彼がいなくなったら?その可能性を考えさせるのだ。
ラスプーチンはエキゾチックな人物だった。「単純で、読み書きがほんの少ししかできない男」であり、その奇妙さは関心と尊敬を集め、彼に向けられる注目とお世辞に耐えるには強い男でなければならなかっただろう。都での生活は、素朴な農民をますます圧倒していった。ラスプーチンは、自分が偉大なことをする運命にあると、すでに信じていたのだ。ラスプーチンはお金よりも、皇帝に仕えツァレーヴィチを守るために神が彼を都に連れてきたという確信に突き動かされていた。ラスプーチンを単なる野心家、人々の信頼を乱用した詐欺師と見なす人もいるが、真実はそれよりはるかに複雑であった。”一見したところ、彼は凍てつく北国の典型的な農民に見えた “とある婦人は回想している。”しかし、彼の目は私の目を捉えていた。その輝く鋼のような目は、人の心の内を読み取るかのようだった”。
ラスプーチンは常に役者であり、自分の役をうまく演じていた。世渡り上手な貴族たちが謙遜やお世辞に感心しないことを知っていた彼は、あらゆる状況を掌握した。ユクスキュル男爵夫人の家に入ったラスプーチンは、ちらっと見て、「これはなんだ?壁に美術館のような絵が飾ってあるじゃないか。壁一枚で5つの村の飢えた人たちを養うことができるのに。農民が食べれずどんな思いをしているか、想像してごらんなさい!」とたしなめた。
罪の意識は強力な武器になった。農民が金持ちや権力者にどう接するべきかという規則を無視し、「ヴィー (vy)」ではなく「タイ (ty)」と呼びかけた。彼は、聖書の知恵の断片を、社会についての観察、精神的な励まし、個人的な質問で挟みながら、次々と話題を変えていった。「あなたの生き方は間違っている!」と彼は何度も叫んだ。「愛がなければだめだ。どういうつもりなんだ?」そのような言説は多くの人を遠ざけるが、中には説得力を感じる人もいた。「グレゴリー神父は人生の鍵を握っている」 「彼は真実を語り、全てを見抜く」と彼らは言った。
ラスプーチンは人々にショックを与えるのが好きだった。彼は馬の性生活を描写するのが好きで、名士の女性を自分の方に引き寄せ、(ほとんど威嚇的に)「さあ、私の可愛い雌馬よ!」と囁くのである。自分の村が神と交わるのに世界で一番いい場所だと言い張った。彼は自分の村が神との交信に最適な場所であると主張した。それとは対照的に、彼の話を聞いていた人たちは軟弱な生活をしていた。「お前たちはもっと単純でなければならない」と彼は言った。「夏になったら、私と一緒にポクロブスコエに行こう。魚釣りをしたり、畑仕事をしたりするんだ。そうすれば、神を理解することができるようになる」。
ラスプーチンは決してハンサムではなかったが、女性を虜にする電気花火のような輝きを放っていた。彼は、王女と農民の区別をつけなかった。ある晩、ニコライ2世が妹のオルガをアレクサンドル宮殿の彼に紹介すると、ラスプーチンはすぐに詮索の限りを尽くして質問を始めた。「あなたは幸せですか?夫を愛しているのか?なぜ彼はここにいないのですか?どうして子供がいないの?」オルガは恥ずかしかったが、ラスプーチンは引き下がらず、しばらくしてソファに座った彼女の肩に腕を回し、なで始めた。オルガは立ち上がって兄夫婦と合流したが、兄夫婦は妹が「かなり気まずい様子だった」という。これは驚くべきエピソードであり、ニコラスとアレクサンドラが “本物のラスプーチン “を知らなかったという説を否定するものである。
サンクトペテルブルクの居間には、夫に浮気された女性たちが大勢いた。彼女たちは社会生活や慈善活動に意義を求め、家庭の幸福に取って代わるものだった。ラスプーチンは彼女たちのニーズを理解していた。 彼女たちの話に耳を傾け、慰めのためにうなずき、正当性を証明し、共感を与えた。彼は質問をし、助言を与えたが、少なくとも初期のころは、彼らの感情のもろさを利用することはなかった。彼は多くの人に、彼らが長い間捨てていた希望を与えた。
何人かの女性たちはラスプーチンの世話をし、贈り物をし、スケジュールを調整し、彼が話す一つ一つの言葉に熱心に耳を傾けた。彼女らは彼の癖を真似ようとさえした。ラスプーチンは彼女たちを “リトルレディ “と呼んだ。
オルガ・ロクチーナはその筆頭である。1905年11月にこの貴族の女性がラスプーチンに会ったとき、彼女は40歳で、彼女自身の言葉を借りれば、”世俗の世の中に幻滅していた”。彼女はまた、重度の慢性腸炎でほとんど機能不全に陥っていた。ラスプーチンは彼女のベッドにやってきて祈った。”私は元気になりました” “その時から病気とは無縁に” と彼女は回想している。ロクチーナと彼女の夫は、ラスプーチンを自分たちのおしゃれなアパートに招待した。ロクチーナは秘書として、彼の予定を調整し、ラスプーチンがぎこちない大きな「G」で署名した手紙に返事を出した。ロクチーナはまた、ツァールスコエ・セローの皇后を訪ね、この農夫の名言と驚くべき性格の物語で皇后を喜ばせた。
アキリーナ・ラプチンスカヤもラスプーチンの側近の一人だった。二人が出会ったとき、31歳で独身だったラプティンスカヤはウクライナの農民で、看護師の訓練を受けており、ラスプーチンの病気や二日酔いを看病していた。彼女は1907年にラスプーチンを異端として調査した委員会に、彼の心には「純粋な愛」があり、彼の周りに集まる女性たちを「愛情深く」扱うことに何の問題もないと言った。
キオニヤ・ベルラツカヤも信奉者の一人である。陸軍中尉だった夫は、彼女の不倫によって打ちのめされ、自殺した。ラスプーチンのところに来たとき、彼女は30歳で、罪悪感でいっぱいだったが、彼は彼女を利用しようとはしなかった。神の慈悲を求め、将来の誘惑に打ち勝つ力を祈るよう勧めた。ラスプーチンとセックスしたことを否定した「リトルレディ」たちは、少なくともこの初期には真実を語っていたのだろう。彼女らはそれがどんな意味であれラスプーチンが「良心で誠実に愛する方法を信奉者に教えた」と主張した。彼女らは彼を “グレゴリー神父 “と呼んだが、それは冗談にすぎなかったという。キスや愛撫、そして浴場への行き来も「私たちの誰にとっても不適切で奇妙なこととは思えなかった」とロクチーナは言う。「悪いこと、汚いことと考えるのは、悪い人たちだけです」と彼女は付け加えた。
ラスプーチンの最も重要な改宗者はアンナ・ヴィルボヴァで、彼女は大きな矛盾を抱えた幼稚な性格の女性であった。彼女は1884年に生まれた。父親はアレクサンドル・タネーエフ、ニコライ2世の官僚で、アマチュアの作曲家であり、その作品は今でもロシアで演奏されている。母親はトルストイ家の出身で、クトゥーゾフ元帥の直系の子孫である。フェリックス・ユスポフ公は、ヴィルボヴァを「背が高く、がっしりしていて、顔はむくむくと光っており、何の魅力もない」と評した。聡明ではない、非常に狡猾でさえある」と評している。1903年、彼女は宮廷に招かれ、フロイラインの称号を持つ侍女となった。
孤独な皇后は、この若い女性に気の合う仲間を見出した。二人は友人となり、ヴィルボヴァは皇室が毎年行っているバルト海クルーズに参加するようになった。アレクサンドラはアンナの素朴な人柄を気に入り、アンナは皇帝のプライベートな世界に突然入り込んだことに興奮した。皇后はアンナに献身的な愛を求め、そしてそれを手に入れた。皇后が、サンクトペテルブルクの洗練された女性たちではなく、アンナと一緒にいることを好む理由は誰にも理解できず、嫉妬が爆発し、悪口を言ったり、アレクサンドラとレズビアンの恋人だという噂が流れたりした。
不幸な結婚が、アンナと皇后の関係を強固にし、ラスプーチンの輪を広げることになった。1906年の秋、アンナはアレクサンダー・ヴィルヴォフ中尉の関心を引く。彼は、皇室に近い女性と結婚することで、出世に有利になると考えていたようで、熱烈に彼女を追いかけた。アンナは恋をしていたわけではなかったが、両親や友人、そして皇后に至るまで、誰もが彼のプロポーズを受け入れるようアンナを促した。彼女はミリツァ大公妃に迷いを打ち明けると、ミリツァはラスプーチンの指導を受けるように勧めた。その会合は、サンクトペテルブルクで最もファッショナブルな通りの一つであるイングリッシュ・エンバンクメントにあるミリツァの宮殿で行われた。
アンナはラスプーチンが「年老いた農民で、痩せていて、顔色が悪く、長い髪と手入れされていない髭を持っている」という表現をした。「農民の長いコートを着ていた」「着古しと旅のせいで黒くみすぼらしかった」 「大きな目をしていた」「光り輝く目だった」「眼窩の奥深くにあり、人の心や魂を見抜くことができるようだった」「私は結婚について彼に助言を求めた」と彼女は証言している。しかし、彼はその結婚が不幸になると予言した。
アンナとアレクサンダー・ヴィルヴォフは、1907年4月30日に結婚した。二人とも、お互いに結婚の準備はできていなかった。花嫁は、ヴィルヴォフは気が狂ったアルコール中毒で、彼女を殴り、インポテンツだったと主張した。真実は不確かである。アンナは、不安定で残忍な夫のうぶな犠牲者として、自分が見られたいように自分を表現していた。彼女は彼とのセックスを拒否していたようだ。1917年の健康診断で彼女の処女性は証明されたが、彼は結局子供をもうけた。アレクサンダー・ヴィルヴォフは、自分のキャリアアップのためにこの状況に耐えようとしたのだろうが、そうはいかなかった。アンナは皇后のために夫を無視し、彼が不満を漏らすと家から閉め出した。1908年に離婚し、この悲しい夫婦の不和に終止符が打たれた。
煩わしい結婚生活から解放されたアンナ・ヴィルボヴァは、皇后のためにすべてを捧げることになったが、アレクサンドラは彼女に宮廷での地位を与えることを拒否した。彼女の唯一の財産は、アレクサンドル宮殿から200メートルほど離れた教会通り2番地にある小さな別荘だったと言われている。アンナの影響力が増すにつれ、職を求める人々やあらゆる怪しげな人々が、この小さな黄色い家に集まってくるようになった。最後の内務大臣だったアレクサンダー・プロトポポフは、この家を「権力への玄関口」と呼んだ。アンナはアレクサンドラとの親密な関係にこだわり、皇后に1日でも会えなくなると、アンナはご機嫌斜めになった。アレクサンドラでさえも、その献身的な態度に疲れを覚え、「無力な子供を扱うのと同じように」友人を扱うこともあった。
アンナはラスプーチンを「天から啓示を受けた言葉を発する聖人」と呼び、心から信じるようになった。彼は無謬に思えた-「知的な人、天賦の才を持つ人、彼の話を聞くのが好きだった」。ラスプーチンに対するアンナの信仰は、アレクサンドラの態度によってどれほど形成されたのだろうか。アンナ・ヴィルボヴァは、ラスプーチンが皇后の人生の中で独特の位置を占めていることを理解していた。しかし、アンナにもラスプーチンに傾倒する心はあった。彼女は彼の知識に感銘を受けていた。ラスプーチンは、正式な教育を受けていないにもかかわらず、「聖書も聖典も、何でも知っていた」と彼女は言う。
ラスプーチンと皇后の関係を最もよく理解していたのはアンナ・ヴィルボヴァであり、未熟であったかもしれないが、その関係について権威ある説明をしている。「ある母親が、この世に生を受けた一人息子があり、弱虫で、いつも命がけで生きていて、その子が突然奇跡的に健康を取り戻したと想像してみましょう。この素晴らしいことをしたのは、医者ではなく、自分の教会の修道士だったとしよう。その母親は、その人をほとんど迷信的な感謝の念を一生抱き続けるのが自然ではないだろうか?少なくとも子供が成長するまでは、その僧侶を自分の近くに置いて、病気が再発したときに彼のアドバイスや助けを得たいと思うのではないだろうか?これが皇后とラスプーチンの真実のすべてである」。
関連記事 ラスプーチンとはどんな人?『ラスプーチン知られざる物語』5
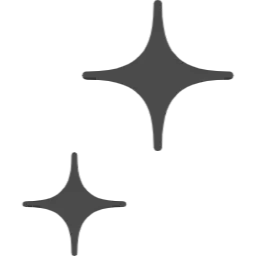
アクセス・バーズはどこから来ているのか?アクセス・コンシャスネスの教えはいったいどこから?
そういった疑問には、やはりこの人【ラスプーチン】を知らなくては始まりません。
ということで、Rasputin Untold Story by Joseph T. Fuhrmann ジョセフ・T・フールマン『ラスプーチン知られざる物語』を読みこもうという試みです。

