2 求道者そして指導者
ラスプーチンは、許しと救いを求め懺悔する放浪者、毎年、帝国中を旅する100万人の一人として、ヴァーホトゥーリエを目指したのだ。フェルホトゥリエまでの325マイルを歩くのに2、3週間はかかったと思われる。夜は納屋で寝たり、道端で丸まったりしていた。ラスプーチンはこの初期に自分自身に多くのことを問い詰めた。しかし、彼の不誠実さを非難するのは難しいだろう。もし彼が単に隣人をなだめる方法を探していたのなら、村からの一時的な追放を受け入れる方がこれより簡単な選択肢だっただろう。しかし、ラスプーチンは求道者であり、これが彼の選んだ道であった。
ラスプーチンは村から村へと移動しながら、自然と交信していたことが想像される。鳥や動物、木々、そして青空や西シベリアの野原や森に咲く花々に神を見出す少年のような熱意を持っていたことがわかる。「自然は神を賛美し、私たちを喜ばせるものだ!」と断言したこともある。「多くの恵みを神に感謝しよう」と力説した。
ラスプーチンはついに目的を果たした。緑の田園風景の中に、ヴェルコチュリエの40の教会、修道院、修道院の白壁と色とりどりのドームが見え、疲れた旅人に手招きをしている。そのほとんどが、聖ニコラス修道院にある聖シメオンの聖遺物を拝みに行く人々であった。ラスプーチンはこの旅の前から、肉を断つために鎖を身につけた若い禁欲主義者、ブラザー・マカーリーと仲良くしていた。マカーリーは読み書きができなかったが、典礼や祈り、聖書の長い一節を記憶していた。彼は広く支持されていた。農民の素朴で疑うことを知らない信仰は、社会全体で模倣されるべきだという正教会の強い流れを、マカーリーは体現していた。彼の演説はまとまりのないものだったが、その言葉には説得力があった。マカーリーは、日常生活の困難と救いの探求との間の類似性を、民衆の言葉で語ったのである。
マカーリーは、キリスト教的生活を求める人々に強い感銘を与え、ラスプーチンはこの悩める時に彼に導きを求めたのである。マカーリーは神の意志を理解するためにたゆまぬ努力を続け、他の人々の探求を手助けする用意があった。彼は神秘主義者であり、神と直接対話することができた。マカーリーは、分別と知恵、祈りと断食の必要性、人間の本性がもたらす誘惑、そして最悪の罪人でも神を見出すことができる方法について話した。
ラスプーチンは農民でありながら、たとえ曖昧な理解であっても、自分には並外れた能力が備わっていると信じていた。少年時代に発揮した力は、彼の人生に対する神の計画の初期の現れだったのだろうか。彼はマカーリーのように、宗教の旅で人々を導くことを意図されていたのだろうか。これがラスプーチンが自分自身の救済を達成する方法だったのだろうか?マカーリーは彼に、神に祈り、霊的な導きを求めるようにと助言した。不安な時代であった。ラスプーチンは後に、「十字架を背負って私に従え」と常に呼びかけてくる内なる声について語った。
「私は、人々がどのように救われるのかを知るために、自分の心を探った」と、ラスプーチンは後に書いている。”私は一生懸命働き、あまり眠らなかった” 洗礼を受けたラスプーチンは生まれながらにしてロシア正教会の信者であったが、その後、自堕落な生活を送り、その教えの多くを無視した。
この旅で思いがけないことが起こった。ラスプーチンは神を見つけたのだ。彼は自分が経験したことの詳細を語ることはなかったが、キリスト教信仰の生きた精神に満たされたと語っている。彼は、キリスト教的生活を送り、神に仕えようと決心した。この時も、どうしたら他の人を真理に導くことができるかを模索していた。
「私はヴェルコトリェで、修道士や兄弟たちと一緒に神を見出した」とラスプーチンは言った。マカーリーの影響は彼の改心に特に重要であり、その結果はグレゴリーがポクロフスコエに戻ったときに明らかになった。村人たちは1917年に調査委員会に、ラスプーチンは大声で淫乱な酔っ払いとして町を出て行ったが、「乱れた髪と無帽で戻り、歌いながら腕を振っていた」と語った。人々は突然、熱狂的な改宗者の炎を燃やし、出会ったすべての人に自分の体験を伝えようとする力強い青年を目の当たりにすることになった。
ラスプーチンは、少なくともこの初期には、精神的な努力に真摯であったようだ。彼はまた、演劇のセンスもあった。彼は、普通の正教徒とは異なる習慣を取り入れることで、自分を宣伝し、評判を上げる方法を知っていた。1903年にサンクトペテルブルクに到着するまで、タバコは止めなかったが、アルコールをやめ、ベジタリアンになった。ラスプーチンは独自の派手な方法で神を崇拝した。村人たちは、彼が村の教会の信徒たちの中に立って、「おかしな視線を横に向けて、しばしば不適切な声で歌った」と回想している。しかし、彼は教会の聖像を一つ一つ丁寧に拝み、祝祭日や断食に参加し、聖歌隊で歌い、信心深さを示すのにふさわしいあらゆる兆候を見せた。また、礼拝の間中、腕を振り回し、不気味な表情をしていた。
ラスプーチンは指導者であり教師でありたいと考えていた。その役割を果たすためには、読み書きができなければならないことを彼は理解していた。彼は、いつ、どこで、どのように「教育」を受けたかについてコメントすることはなかったが、おそらく1897年にヴェルコトリェで2、3ヶ月の間に受けたのであろう。これは困難な過程であったに違いなく、ラスプーチンは決して教養と呼べるようなものにはならなかった。しかし、彼は使える時間の中でできる限りのことをやり遂げたのである。
ラスプーチンはポクロブスコエに戻った後、「私はよく本を読んだ」と語ったが、その後、教父や聖書の引用ができるようになったことも、その主張を裏付けている。彼は教育を高く評価していたのだ。数年後、彼はポクロブスコエに向かう蒸気船で一人の男とその息子に出会った。息子はノートを持っていて、すれ違う船の名前を書き留めていた。ラスプーチンは、「文盲はきびしいぞ!」と言いながら、学校に残り勉強するように促した。
運命的なものを感じたラスプーチンは、ポクロフスコエに自分の意見を受け入れ、指導を受けようとする少人数の人々を集めた。イリヤ・アルセノフ、ニコラス・ラスポポフ、コルチャコフ一家、ペチェルキン姉妹のカトリーヌ(カーチャ)とエヴドキーヤ(ドゥーニャ)などが彼の信奉者たちであった。彼らは、たとえそれが伝統的な正教の枠を超えていたとしても、神とのより濃密で個人的な関係を求めるラスプーチンについていく覚悟があった。彼らの会合が秘密であったことは、グループの成長を遅らせたが、そのおかげで当局が彼らの活動を妨害することはなかった。ラスプーチンは、信奉者と裏で絆を深めることが、彼らに対する自分の権力を強固にすることも理解していたに違いない。
さっそく憶測が飛び交った。グリシュカは何をしようとしていたのか?人々は、ペチェルキンの少女たちがラスプーチンを浴室で洗う儀式を行い、他の人々は彼の父親の家の地下室に集まったという噂がささやかれた。姉妹が歌いながら厳粛にラスプーチンを聖像で飾られた簡素な祭壇に案内し、ラスプーチンは聖書を読み、説教をした。信者たちは祈り、賛美歌を歌った。その音楽は奇妙で耳を疑うようなもので、ロシア正教会のものではなかった。村人たちは、ラスプーチンが悪名高い宗派のグループ、クリストに加わっているという結論に飛びついた。しかし、それは事実ではない。
しかし、ラスプーチンの信念を形成する上で、クリストは重要であった。ラスプーチンは最後までロシア正教会の信者であったが、活発で好奇心旺盛な性格から他の教義にも関心を持った。改宗後、ポクロブスコエにやってきたバプテスト派や福音派のキリスト教徒に耳を傾けた。また、アバラーク修道院で異端として投獄された司祭ヤコフ・バルバリンから多くを学んだ。宗派もまた、彼の考えを形成した。彼らは、1650年代に総主教ニコンが宣言した改革を拒否した分裂主義者である旧信徒とは全く異なっていた。旧信者たちは、自分たちは正統派の信仰を本来の純粋な形で維持し、正統派の伝統の中で礼拝を行うということを主張した。これに対し、宗派の人々は、ロシア正教会の一員では決してなかった。
1617年頃、農民であったダニエル・フィリポビッチが自らを “生き神 “であると宣言したことから、クリスト派は始まった。彼は、男性だけでなく、他の普通の人々、女性もこれらの神の贈り物を持っていると宣言した。彼らは自らをキリスト信徒と呼び、フィリッポビッチが正教会の異端から導くために遣わされたのだと確信した。しかし、この宗派はシベリア全土で繁栄し、政府の永遠の悩みの種となった。
敵は彼らをクリスト(Khlysty)と呼んだ。クリスト(khlyst)とはロシア語で「鞭」の意味である。彼らの集会は “船 “と呼ばれていた。信者は夜、地下室や貯蔵室で集会を開いた。白いローブを着たキリストを信じる者たちは、「キリスト」または「神の母」と呼ばれる男性または女性の指揮のもと、賛美歌を詠唱した。鞭を持った指導者が血の気が引くまで鞭打つと、クリストは叫びながら腕を振り、狂喜乱舞した。恍惚の境地に達すると、祭司たちは衣を脱ぎ捨て、手近にいる者と性行為に及ぶ。
クリストは、結婚してもセックスは罪だと考えていた。しかし、キリストを信じる者たちは、罪によって神から引き離されることはなく、罪によって悔恨の念を抱き、神の恵みを乞うた。彼らは罪が、そして罪だけが、救いをもたらすと主張した。逆説的だが、救われるためには、ラジンスキーが「闇の勇気」と呼ぶ、罪を犯すことを呼び集める必要があった。
ラスプーチンがクリストの一員であったというとがめは、彼の人生の最後までつきまとった。彼は彼らの思想と実践の要素を取り入れた; 彼は酒とタバコを拒絶し、彼の信奉者たちは互いに「兄弟」「姉妹」と呼び合っていた。彼のサークルは地下室で会合を持ち、クリスト賛歌を歌った。しかし、度重なる調査でも、ラスプーチンがこの宗派のメンバーであったことを証明することはできなかった。実際、ラスプーチンの礼拝にはセックスが含まれていなかったのは興味深いことである。ラスプーチンはクリストに好意的であったが、その集団に入れば、エリート界で影響力を持つようになる望みが絶たれることを十分理解している抜け目のない人物であった。しかも、ラスプーチンはリーダーであって、フォロワーではなかった。つまり、彼は自分の思想体系を作り上げ、自分の信奉者のグループを集めなければならなかった。
ラスプーチンは、1898年に幻視を見たと主張した。ある日、畑で仕事をしていると、目の前に聖母マリアが現れ、空を舞っていると信じた。彼は膝をついて指示を待ったが、聖母はただ地平線を指差しただけだった。彼は、聖母の仕草を、再び巡礼の旅に出るようにとの呼びかけと受け取った。この体験は、彼の人生を大きく変えた。ラスプーチンはマリアへの帰依を強め、マリアが常に自分を導き、指導してくれていると感じるようになった。「母なる神の聖像を部屋に置いて一晩過ごしたこともある」と彼は回想している。そして「私は人類の罪のために泣いています、グレゴリー。行きなさい、さまよい、人々の罪を清めなさい 」という声とともに、マリアが涙を流しているのを見た。
ラスプーチンは、そのとき彼の魂を襲った神秘的な感覚を聞き手に印象づけるかのように、しばしばその幻影を語っている。それは彼を運命の人として刻印し、自分には歴史的使命があるという確信を強めた。ロシア正教は奇跡や幻視を神の恵みの現れとして受け入れている。1900年頃、ラスプーチンは突然、神が東方正教会の修道院の中心であるギリシャのアトス山に巡礼するよう自分に呼びかけていることを告げた。
エフィム・ラスプーチンは、息子が「怠け者の巡礼者」になってしまったと嘲笑した。その評価は妥当ではなかった。ラスプーチンは、雨の日も晴れの日も、村や田舎を何百マイルも歩き、常に雑用と施しを当てにすることを提案していたのだ。農民としての生活は大変だったかもしれないが、ラスプーチンが提案した巡礼の旅よりは楽だったに違いない。
こうしてラスプーチンは、ストラニク(巡礼者)としてギリシャに旅立った。このような男女が、靱皮の履物と、農民服を着て、少ない所持品をナップザックに入れ、肩から下げて歩いているのをよく見かけた。”巡礼の道”は彼らの天職であり、それを追求することに熱心であった。彼らは快適さや喜びを求めず、イエスの祈りを延々と繰り返しながら、質実剛健な生活を送っていた。「主イエス・キリストよ、罪人(ざいにん)を憐れみ給え」。ラスプーチンは彼らの召命を喜んで分かち合った。
「この間、私は猛烈に人生を受け入れてきた。「良いことも悪いことも、すべてに興味を持ち、すべてを受け入れ、何も疑わなくなった。嵐も風も雨もものともせず、1日に40?50マイルも歩いた。食事はほとんど取れず、タンボフではジャガイモしか食べられなかった。お金もないし、時間の心配もない。神様が与えてくれるものだから、一晩の宿が必要なら寝た。彼は半年間、下着を換えず、自分を構わずに過ごした。毎晩、聖書の一節を読み、祈り、導きを求めながら、ロシアを横断して歩いた。数ヵ月後、彼の決意は弱くなった。
「お前はうまくやってるな」というささやき声が聞こえた。ラスプーチンは、それが悪魔の声であることを知っていた。「でもお前が何をしてるか誰も知らないぞ」と続いた。これは彼の人生のどん底であり、疑心暗鬼の時であったが、彼はそれを克服した。 彼の旅は困難なものであったが、愛の鎖で縛られた闘いから抜け出した。そして、神の目的を発見するために必要な、肉体的、精神的な献身を呼び覚ましたのである。
シベリア、ウクライナと渡り、ラスプーチンはついに正教会の修道院であるアトス山に辿り着いた。当時は修道士になることも考えていたというが、指導者を目指す人間がそんなことをするわけがない。ラスプーチンは、この訪問を誇りに思っていたが、修道士の中に同性愛を公言している者がいることを知り、反発を覚えた。ラスプーチンは初めてそのような習慣に触れ、罪や性に対して柔軟な考えを持っていたにもかかわらず、深く幻滅して聖山を後にした。数ヵ月後、彼はついにシベリアに到着した。彼は自分の体験をマカーリーに伝えるため、ヴェルコトゥリエに行かねばならなかった。マカーリーは、ラスプーチンのアトス山での生活の描写にショックを受けた。それでもマカーリーは、彼の未来には偉大なことが起こると断言した。「自分の使命を忘れるな、修道院で救われることはない。この世で魂を救え」と。
ラスプーチンはポクロブスコエから2年近く離れた後、アトス山を訪れ、彼にとって最長の巡礼の旅となった。彼が出発したときマリアはまだ数ヶ月だったので、それは1898年であったはずだ。彼が戻ってきたとき、娘は「長い茶色の髭を生やした背の高い男」と「疲れた顔」が、明らかに疲労困憊したようすで帰ってきたのを覚えている。”グレゴリー!” と、プラスコバヤは叫んた。マリアは驚いて、母が夫の腕の中に身を投げているのを見た。このような不在はプラスコバヤにとって辛いことだったが、マリアは母が夫を誇りに思っていたことを回想している。
ラスプーチンはポクロブスコエで敵意をあらわにした。彼はしばしば村に戻り、村が疑心暗鬼に包まれているのを発見した。 彼はよく修道女の服装に似た若い女性を連れているたため、敵に弾みをつけてしまったのである。 そして、人々が驚きをもって見守る中、別れのキスをした。少なくとも、彼女らは喜んでパートナーになったのだ。しかし、ラスプーチンが彼女を地下室に連れ込み、レイプしたと報告した若い女性の場合は、そうではなかった。最後に彼は泣きじゃくる少女に、自分たちのしたことに罪はない、単に三位一体を祝っていただけなのだと言った。
ラスプーチンは既婚者でありながら、他の女性を追い求めた。時には、誘惑に勝てるか、女性に服を脱いでもらい、体を洗ってもらうこともあった。ラスプーチンは異常に強い性欲を持っていた。これは非常に顕著で、彼の人生のあらゆる面に影響を与えた。彼は自分が罪人であることを自由に認め、罪に抵抗すべきであると信じていた。ある時はそれに成功し、またある時は防御が崩れ、パートナーとセックスをした。ラスプーチンは、そのような罪は、神の人である自分が裁きの上に立つため、自分で背負ったのだと説明した。ラスプーチンは情熱的で、衝動的で、葛藤があった。彼は日々、自分の衝動を抑えるのに精一杯だった。ラスプーチンは常に自分の暗黒面を受け入れ、それをまた神が与えた試練と考えた。ラスプーチンにとって、セックスは喜びではなく、精神的な負担であることを理解していたのは、プラスコバヤだけであった。ポクロブスコエの主任司祭であるペテロ・オストロモフ神父は、そのような微妙なことには関心がなかった。マリアはオストローモフ神父のことを、「祈りの言葉をつぶやくことが人生の目的だと思っているような」厳格で禁欲的な人物と記憶していた。オストルーモフは、この非正統派的な宗教と官能的な情熱の融合に激怒した。
スキャンダルはラスプーチンに迫っていた。冷笑は認知と地位を切望する男にとってあまりに酷かった。自分の村では相手にされないのなら、ラスプーチンは村を出なければならなかった。そして1902年、ラスプーチンはブーツについたポクロブスコエの埃を振り払い、シベリアの向こうに広がる大きな世界へ向かう旅に出たのである。
カザンは、ヴォルガ川のほとりに広がる人口の多い都市で、神学院もあった。ラスプーチンがこの街に到着する頃には、人々は彼をスタリエタスと呼んでいた。スタリエタスとは、強力な祈りの生活を特徴とする神秘的な資質を持つ男女に人々が与える称号である。ラスプーチンは型破りな恋愛をしていたため、そのような名誉は問題外だと思われるかもしれない。しかし、ラスプーチンの性格には相反するものがあり、ポクロブスコエの外の人々は、なぜかラスプーチンを神の人として注目したのである。とにかく、彼らは彼を “スタリエタス・グレゴリー “として受け入れていた。フョードル・ドストエフスキーは『カラマーゾフの兄弟』の中で、スタリエタスとは “あなたの魂と意志を彼の魂と意志に取り込む者 “であると述べている。スタリエタスは教師と精神的指導者の役割を兼ね備えており、祈りと宗教的指導を提供し、信者が人生の不確実性を乗り越えて救われるように導く存在であった。
ラスプーチンはカザンに到着したとき、33歳だった。帝国の道路や脇道をとぼとぼ歩いていた年月が、今の彼に有利に働いている。風と太陽は彼の肌を日焼けさせ、痩せ細った顔を引き締めた。シベリアのムゼキは、かつて農奴制の下にあった西部の同胞とは異なり、独立した気風を持ち、誇りをもって生活していたからである。ラスプーチンは自信と権威を振りまき、あらゆる状況をコントロールすることを期待した。多くの人がその明るく輝く瞳に魅了された。ラスプーチンが何を言ったかは、聞く人が聞きたいことを確かに聞いたという事実ほど重要ではない。
しかし、ラスプーチンが常に好印象を抱いていたわけではない。彼の髪は脂ぎった束で垂れ下がり、指の爪は農作業で黒ずんでいた。髭はその日に食べたものを表していると言われた。ラスプーチンは強烈で不快な香りを放っていたと言われることがある。カザンに落ち着くやいなや、彼は浴場を頻繁に利用した。彼がだらしなく、臭かったとは考えられない。むしろ、ラスプーチンは自分の外見に虚栄心を抱いていた。常に髪をとかし、衣服やブーツの贈り物を熱心に受け取っていた。常に期待に応えようとするラスプーチンは、この新しく洗練された世界を征服する決意をもって、この世界に飛び込んでいった。
ラスプーチンは、教会が危機に瀕している時に現れたことで得をした。正教はロシアの公的な信仰であり、国家と密接に結びついている。政府に対する批判の高まりは、人々の教会に対する姿勢に影響を与えた。正教会は堕落した修道士や神父の集まりで、警察の情報屋に過ぎないと考える人が多くなっていた。また、煌びやかな法衣や華麗な儀式が、一部の信者の心を離れさせ、その答えを求めて、別の場所に足を運ぶようになった。1830年代にニコライ1世が始めたスラブ復興運動は、ロシアの偉大さを取り戻すために、教会の導きのもとで主権者と一体となった英雄的で簡素な過去へのアピールをもっていた。このノスタルジアの究極の象徴が農民であり、神話では揺るぎない忠誠心と深く疑うことを知らない信仰心に満ちているとされた。ロシア人の中には、人生の深い問いに対する答えを科学に求める者もいたが、教会は庶民の中に価値を見出した。農民は神に近いと言われた。彼らの敬虔さは見習うべきものであり、彼らの知恵には単純明快な優しさが宿っていた。カザンの人々は答えを求め、ラスプーチンはそれを提供する準備ができていた。放浪の巡礼者や聖人はよくいるものだが、ラスプーチンは特別な印象を与えた。彼は大胆に行動することを学んだ。謙虚さやお世辞は神の使命を担う人間には不要であることを理解していたため、彼はぶっきらぼうで、自分だけがルールを決めるゲームをすることに固執した。教会の指導者やエリートには、農民と同じように親しみを込めて接した。
その特徴は、女性の手を取り、顔をじっと見つめながら、心の奥底を探るような目をしていることだ。彼の質問は、女性を不快にさせたかもしれないが、彼女の問題の真相を探るものであった。ラスプーチンは好戦的であると同時に、安心させるような態度をとることもあった。彼の直感は、人を分析し、適切な言葉や身振りで対応することを可能にした。そのため、彼のもとに指導や慰めを求めてやってくる感情的にもろい人々の多くに対して、優位に立つことができた。
ラスプーチンはおもしろい人で、彼と一緒にいるのは楽しいことだった。彼は人々にあだ名をつけたが、それはしばしば斬新でかなり適切なものであった。彼は女性に “そそられる女”、”女親分”、”色っぽい子”、”べっぴんさん “などのあだ名をつけ、男性には “上層の方”、”貫禄さん”、長髪”、”同志 “などのあだ名をつけた。これを人々は、農民のユーモアと受け止め、軽蔑の念を抱くこともなく、魅力的なキャラクターとして受け止めていた。ラスプーチンは、カザンですぐに霊的な深みを持つ人物として地位を確立した。短期間のうちに2人の子供を失った若い夫婦が、この訪問の際に彼のもとを訪れた。「妻の絶望は狂気へと発展し、医者も何もできなかった」と夫は回想した。”ある人が私にラスプーチンと会うようにと助言したんだ。. . . 想像してみてほしい:30分ほど話した後、彼女はすっかり穏やかになったのだから。彼を悪く言うのは勝手だが、もしかしたらそうかもしれない。しかし、彼は私の妻を救ったのだ。それが真実だ!”
カザンでは、ラスプーチンが女性との付き合いを楽しんでいるという噂が絶えなかった。彼は彼女たちの手を握り、親しげにキスをしたとされているが、この件に関して彼には弁護者がいた。ある女性は、ラスプーチンがベッドを共にしたと人々に話した。しかし、彼の目的は、そのような状況下でも誘惑に耐えられることを示すことだった。性的なことは何も起こらなかった。それはそれで面白いのだが、ラスプーチンはいつもそんなにきちんとしていたわけではない。二人の姉妹(一人は20歳、もう一人は15歳)がカザンの浴場で彼に進んで身を委ねた。それを知った母親は急いでその場所に向かったが、3人が帰ろうとしているところに出くわした。「ラスプーチンは悪意のある笑みを浮かべて言った。「さあ、これで安心だ。「娘さんたちに救済の日が来たんだ」。
こうした不祥事にもかかわらず、ラスプーチンは強力な魔力をかけ、多くの人がその魔力に屈した。彼はカザン郊外にあるセブンレイク修道院の神父ガヴリールの支持を得て、その名声を大いに高めた。ガヴリルはこの新参者と彼の霊的な才能、そしてラスプーチンが異端者で女性の信者とセックスしているという噂を聞きつけたのである。ラスプーチンは、ガヴリルにそのことを問いただされたとき、率直に、自分が罪人であることを認めた。そう、彼は女性にキスをし、愛情を持って接した、しかし彼らの関係は常に適切であったと彼は主張した。ラスプーチンはクリストであることを否定した。最終的にガヴリルを動かしたのは、ラスプーチンがフィリップ神父について 述べたある予言だった。ラスプーチンはその神父に、若い修道士フィリップについて「気をつけるように」と警告した。その言葉は奇妙で、ラスプーチンは自分でも説明がつかないと認めた。ガヴリルはそれを笑い飛ばした。だが数日後、フィリップはガヴリルにナイフで襲いかかった。ガヴリルは、ラスプーチンが予知能力と神秘的な才能に恵まれた真のスタリエタスであると確信するようになった。
ラスプーチンは、カザン司教のアンドリューにも大きな印象を与えた。ラスプーチンは、ロシア正教会が信徒との新しいつながりを求めている人物にまさにふさわしいと思われた。アンドリューは、ラスプーチンがサンクトペテルブルクの教会指導者を訪問することを強く希望した。アンドリューのスタッフがラスプーチンに同行して、アレクサンドル・ネフスキー修道院にある神学院の院長セルゲイ司教を訪ねた。ラスプーチンの過酷な旅の日々は、もはや過去のものとなった。一等列車の客車で快適に移動していた。ラスプーチンは自らを「道行く盲人」に例えたが、その道は彼にとって憧れの道であった。
ラスプーチンは1903年の四旬節にサンクトペテルブルクに到着した。彼は生まれて初めて、100万人以上の人口を抱える本物の大都会に直面した。サンクトペテルブルクは19の島に広がり、運河には繊細な橋がかかり、ネヴァ川によって半分に分断されていた。それは、ロシア的なものと正反対であった。ピョートル大帝は、モスクワの狭い道と中世の雰囲気を拒絶して、この新しい首都を築いたのである。貴族は常に政府に文句を言い、互いに謀略をめぐらし、聖職者は自分たちの特権を守ることにしか興味がないようだった。
一方、サンクトペテルブルクの街は広く、イタリア人建築家が設計したバロック様式の宮殿が並んでいた。貴族は国家に仕え、教会は独立を奪われ、皇帝の圧制的な官僚機構の一要素に過ぎなかった。サンクトペテルブルクは快楽主義的で、人工的で、シニカルで、大いなる特権と厳しい絶望が混在していた。サンクトペテルブルクは、ラスプーチンが最も偉大な役割を果たす舞台となるのである。
ラスプーチンの当面の目的地は、帝国の四大宗教センターの一つであるアレクサンドル・ネフスキー修道院であった。彼は聖堂で他の参拝者とともにロウソクを灯し、祈りを捧げた後、着替えをしてセルゲイ司教に会う準備をした。ラスプーチンはアンドリュー司教からの手紙を携えており、そこにはラスプーチンのことをスタリエタス、疑いない洞察力と精神的な知恵の持ち主であると書かれていた。アンドリューはサンクトペテルブルクの教会指導者たちに、彼の霊的な才能は教会が庶民との結びつきを強めるのに役立つから、彼の言葉に耳を傾けるようにと助言している。ラスプーチンとセルゲイは長い間話をした。農民は聖書、教会の教え、日常生活の課題について語り、セルゲイは「神はしばしば普通の人を通して働かれる」という古い格言を思い起こした。司教はラスプーチンに感激し、彼を自分のアパートに招いた。
それから間もなくのある夜、セルゲイはラスプーチンを他の司教たちに紹介した。「彼らは学識と教養のある人たちだった」と目撃者は回想している。彼らは権威に慣れているが、その夜、彼らの役割は逆転した。ラスプーチンは注目の的であり、それを楽しんでいた。彼は自分の意見を述べ、自分の経験を話し、質問に答え、聞く人が彼の中に何を見いだしたいと思っているかを誘うようなやり方で自分を見せた。楽しい夜が終わろうとするとき、ラスプーチンは3つの予言をした。それは奇妙なもので、人は彼が恐ろしい危険を冒して予言したのだと思っただろう。ラスプーチンは、ある司教はまもなくヘルニアになり、別の司教は母親を失い、3人目は婚外子の父親となると言った。ラスプーチンにまつわる言い伝えでは、これらの予言はすべて的中したとされている。真実かどうかは別として、このエピソードはサンクトペテルブルクの正教会のエリートたちの間で彼の評判を確固たるものにした。
ラスプーチンはクロンスタットのヨハネ神父にも会った。ヨハネは演説の才能と貧しい人々のために働くことで広く崇拝されていた人物である。ヨハネはアレクサンドル3世と親しく、アレクサンドル3世はヨハネに最後の告解を聞くよう依頼した。伝説によると、ラスプーチンはヨハネの説教を聞くためにフィンランド湾に浮かぶコトリン島の聖アンデレ聖堂を訪れ、大勢の信徒と牧師の真摯な言葉に感銘を受けたという。礼拝中、ヨハネ神父は、霊的な賜物を持つ者の存在を感じ取ったので、その者に前に出るようにと言ったとされる。ラスプーチンは前に出た。ヨハネは、彼を祝福し、神の召しを全うするように促した。この話は確かなものではないが、ラスプーチンはしばしばこの話を自慢し、神が自分を民衆の宗教生活における特別な役割に選んだという証拠に挙げたという。
1903年、イリオドールという若い学生が、アカデミーでラスプーチンに出会った。1880年にセルゲイ・トルファーノフとして生まれたこの修道士は、燃えるような信念と途方もない野心を抱えていた。イリオドールはラスプーチンと親交を深め、やがて反目し、極端な言葉でラスプーチンを糾弾するようになる。イリオドールが「シベリアから来たグレゴリー神父」と初めて会ったときのことを語るとき、回顧的な判断が感じられる。ラスプーチンは「質素で安っぽい灰色の上着を着ていた」、「ズボンは荒い男物のブーツの下に入っていた」、「不快な臭いを放っていた」と言われている。しかし、イリオドールはラスプーチンがアカデミーの教授陣と学生に感銘を与えたと認めている。
ラスプーチンがサンクトペテルブルクで掌中に収めた最も重要なものは、フェオファン大司教であった。彼は神学院の監察官であり、皇帝夫妻の聴罪司祭であった。フェオファンは学生たちに「神は遠いシベリアから偉大な人物をよみがえらせようとしている」「ラスプーチンはロシアの救世主になるだろう」と語り、目に見えて興奮した。ラスプーチンに会ったフェオファンは、この農夫の心理的な洞察力に目がくらんだほどだった。ラスプーチンの「顔は青白く、目は驚くほど鋭く、断食を守っている人のような顔をしていた。そして彼は強い印象をもたらした」。イリオドールによると、フェオファンはラスプーチンに自分のアパートをシェアするように頼んだ。
ラスプーチンはその誘いを受けた。セルゲイ司教は人気があり、影響力もあったが、ラスプーチンのキャリアを前進させるのに最大限の価値を発揮するには、少し闘争心が強すぎたようだ。一方、フェオファンは、貴族のサロンや皇居に出入りする人たちなど、社会的なコネクションを持っていた。フェオファンはセルゲイにはできない方法でラスプーチンのために扉を開いた。ラスプーチンはすぐにその好奇心で多くの偉い人たちと会い、新しい道を切り開くことができた。それはラスプーチンの人生にとって極めて重要な瞬間であり、彼はそれを知っていた。彼は後に、サンクトペテルブルク・アカデミーでフェオファンやその仲間たちと過ごした日々に「大学は卒業だ」と宣言している。
フェオファンは、ラスプーチンを宗教に関心のある社交界に送り込んだ。”ロシアの教養のある階級は、教会に熱烈な愛着を抱いているものの、我々が一般的に使うような意味での宗教性は全くない “と、あるイギリス人訪問者は断言している。ラスプーチンがカザンで遭遇した懐疑的な雰囲気は、首都ではさらに顕著であった。貴族たちは退屈し、新しい体験を求めていた。彼らは正教を迷信に染まり、伝統に堕落した農民や司祭の信仰と見ていた。降霊術や東洋の神秘主義が流行した。ラスプーチンは、豪華な宮殿や精巧な調度品のある応接室に立ちながらも、神との霊的な交わりを主張する男として広く歓迎された。
その「真実の探求者」の一人が、モンテネグロのミリツァ大公とアナスタシア大公の姉妹である。彼女たちは、バルカン半島の無名で貧しい王国に生まれた。アレクサンドル3世は、彼女たちをサンクトペテルブルクに呼び寄せ、名門スモリニー学院で教育を受けさせ、庇護者の役割を果たした。1889年、姉妹は戦略的な結婚によって社会的地位を確立する。ミリツァはニコライ2世の再従兄弟にあたるピーター・ニコラエヴィチ大公と、アナスタシアはロマノフ家のロイヒテンベルク公爵と結婚した。彼女たちは、その黒い顔立ちから「カラス」「黒真珠」と呼ばれ、「黒豹」とも呼ばれた。実はミリツァは世界の偉大な宗教を真剣に研究しており、ラスプーチンに興味を抱いた。「彼の演説は非文法的で、預言者のように思わせるイメージに満ちていた」と後に語っている。”グレゴリーの福音書、特に黙示録の解説は鋭く、独創的だった”。
ラスプーチンは、自分のキャリアアップのために人を利用したり、捨てたりすることに長けていた。ラスプーチンはフェオファンと暮らすメリットを使い果たすと、マスコミで彼を宣伝できるジャーナリストであるG・P・サゾノフのもとに身を寄せた。新聞に好意的に取り上げられると、彼の神秘性が増し、人々の好奇心が増す。ラスプーチンはサゾノフのアパートで女性を迎えることもできたが、フェオファンのアパートではそうはいかなかった。
ラスプーチンは、サンクトペテルブルクでの生活を続けることもできただろう。しかし、数ヵ月後、彼は驚くべき決断をした。ポクロブスコエに帰郷するのだ。おそらく彼は、このような強力な界隈での活動のプレッシャーに圧倒され始めたのだろう。また、後に彼がしばしばしたように、シベリアのルーツに再びつながり、自分の村の簡素な生活の中で肉体的、精神的回復を得る必要性を感じたのだろう。いずれにせよラスプーチンは、時期が来ればサンクトペテルブルクに戻れると思っていた。
ラスプーチンは1903年の秋にポクロブスコエに帰ってきたのだが、彼は別人のようになっていた。まずカザンを征服し、次にサンクトペテルブルクに旋風を巻き起こしたのである。彼の衣服は、彼の生活の変化を最も具体的に示すものであった。彼の崇拝者たちは、首都で最も高級でファッショナブルな店で、彼にいくつかのワードローブを買い与えた。ラスプーチンはカラフルな絹のシャツに鮮やかな帯をかけ、輝く革のブーツを履き、さらにおしゃれなズボンと幅広の革ベルトを身につけるようになった。かつて、この「預言者」を不愉快に思っていた村人たちは、抑えた。村人たちは、彼の功績を認めざるを得なかった。放蕩息子は再び故郷に帰ってきたのだ。
つづきを読む ラスプーチンとはどんな人?『ラスプーチン知られざる物語』3
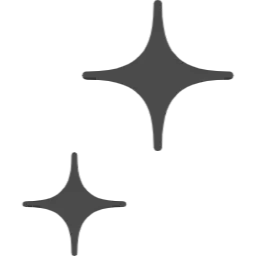
アクセス・バーズはどこから来ているのか?アクセス・コンシャスネスの教えはいったいどこから?
そういった疑問には、やはりこの人【ラスプーチン】を知らなくては始まりません。
ということで、Rasputin Untold Story by Joseph T. Fuhrmann ジョセフ・T・フールマン『ラスプーチン知られざる物語』を読みこもうという試みです。

