6. ロマノフの聖なる愚者
ラスプーチンが教会の敵に勝利したことを喜ぶのはまだ早かった。彼がポクロブスコエに留まっている間にも サンクト・ペテルブルクでは 彼に対する別の作戦が立てられていた。 今回は賭けの対象がさらに大きくなり、無罪の推定はありえない。首相であるピョートル・ストイピンはラスプーチンの政治的キャリアに突然の終止符を打つことにした。
ラスプーチンがツァールスコエ・セローに行くことは、警察の注意を引くことになった。確かに彼の訪問は秘密ではなかった。ラスプーチンの姿はツァールスコエ・セロー鉄道駅で見ることができ、彼の車は公道を通り、様々な障壁や門で拘束された。ラスプーチンはアレクサンドル宮殿の脇の入り口を使ったが、当直士官が電話で許可を出す間、検問所で待っていた。ラスプーチンの行動は公開され、厳重に監視された。
その頃、政府関係者はピリピリしていた。政権が戦争と革命をかろうじて乗り越えてきた時代であり、皇族が屋敷を離れると暗殺に遭うこともあった。ある秘密警察官(オクラホマ)は、1908年当時、「新参者はみな否定的な目で見られた」と回想している。聖職者がテロリストになるかもしれないし、外国の諜報員はどこにでもいると思われていた。宮廷司令官で皇室の警備を任されていたウラジーミル・デディユリンは、すぐにラスプーチンを疑った。彼はラスプーチンが「アンナ・ヴィルボヴァの後援を受けている」と考えたが、警察が彼女とその動機について同様に懐疑的であったことを考えると、推薦とは言い難い。デディユリンは警察にラスプーチンの経歴を調べるように命じた。
デディユリンは、その結果をストリピンに報告し、ストリピンは独自に調査を開始したようだ。宰相は、貴族の家系でありながら、知力、能力、財力によって官僚の頂点に立った巨大な権力者であった。ストリピンは皇帝への忠誠心が強く、先見の明のある改革と残忍な弾圧の組み合わせによって、皇帝の座を強化しようと考えていた。彼は、ロシア社会のある種の大改革が、帝政を強化することを理解していた。ストリピンはラスプーチンと彼の周りに渦巻く噂を、彼の目標に対する障害と見なした。
ストリピンはデディユリンの調査範囲を拡大した。報告書は消えてしまったが、ラスプーチンを否定的に紹介したものと思われる。帝都警察は巧妙な手口で、刑事の着ている服からも面白いほど見えてしまう。ラスプーチンはニコライに文句を言い、ニコライは次の報告でストリピンにこの問題を取り上げた。しかし、宰相はアレクシスが血友病を患っていることを知らなかった。もし、両親がこのことを公表していれば、ラスプーチンが頻繁にアレクサンドル宮殿に滞在していた理由を世間は理解できただろう。しかし、それは推測に過ぎない。ニコライ2世は、なぜ人々がこの地味な農民に執着するのか、理解できなかった。ニコライはラスプーチンを神の人、民衆の代弁者と見ていた。甘かったが、皇帝はストリピンがラスプーチンに会えば、同じ理解に至るだろうと考えた。
ストリピンは、内務大臣補佐官で職権上の警察長官であるポール・クルロフを同席させ、渋々ながらも皇帝の要請を断りきれなかった。奇妙な出会いであった。クルロフはラスプーチンのことを「痩せた普通の男で、濃いくさび形のひげを生やし、鋭い知的な目をした」と回想している。ラスプーチンは、自分は政治的な意図のない平和主義者であり、警察が心配する必要はないと断言した。首相は「もしそれが本当なら、ラスプーチンは警察を恐れる必要はない」と答えた。このことは明らかにラスプーチンを不安にさせ、この時点でストリピンに魔力をかけようとした。首相は娘に「彼は青白い目を私の上に走らせた」と語った。「彼は聖書の中の不可解な言葉をつぶやき、両手で奇妙な動きをした」。ラスプーチンの催眠術の力はストリピンを驚かせた。そして、この「害虫」に多大な「嫌悪感」と「反感」を抱いた。それが、その後の紛争への対応のまずさを物語っているのだろう。
気を取り直したストリピンは、ラスプーチンを非国教徒として起訴するのに十分な証拠が揃っていると宣言した。ラスプーチンは首都を離れるか、告訴に直面するか、それは彼の選択であった。ラスプーチンは暴動を起こし、ストリピンはクルロフに、皇帝のために自由に使えるすべての情報を集めた書類を作成するよう命じた。「私はストリピンにそうしないように忠告した」とクルロフは書いている。「ニコライは、人々が単に自分の好きな人の信用を落とそうとしていると結論づけるだろうからだ」。実際、皇帝はラスプーチンが攻撃されたことを快く思っていなかった。ストリピンは皇帝への次の報告で、不意にラスプーチンとその悪質な影響力について語り始めた。ニコライは驚き、黙っていたが顔には不愉快そうな表情を浮かべていた。ニコライは、この問題がストリピンの頭痛の種であり、執拗に追及してくることは明らかだったので、ラスプーチンに二度と会わないことを約束し、譲歩させた。
ラスプーチンに対するストリピンの憎しみは彼の判断に影響を与え、ラスプーチンと接触しないようにという皇帝の約束を、ラスプーチンに対する行動を起こすことの許可と読み取った。ストリピンは、この農民を5年間首都に立ち入らせないという勅令を出した。ラスプーチンはストリピンがこの処分を準備しているとき、ポクロブスコエにいた。警察はラスプーチンがサンクトペテルブルクに戻った瞬間に書類を送達するために駅で待機していた。ラスプーチンは警戒しており、列車が駅に入るやいなや、待っていた車に飛び乗り、ニコラーシャとアナスタシアの家に急行した。警察は皇帝の命令なしに皇居に入ることはできないので、オクラホマは宮殿の外に捜査官を配置し、農民が現れたら逮捕できるように待機させるしかなかった。しかし、ラスプーチンはその網をかいくぐって列車に乗り込み、ポクロブスコエに帰ってしまった。ストリピンはロシアの歴史の中で巨大な力を持っていた。革命を打ち負かし、1906年と1908年から続く暴動を鎮圧したのである。しかし、一人の農民が彼を追い詰めた。ストリピンは、ある将校から「シベリア出兵はどうするのか」と問われ、「無駄だ」と答えるような仕草をした。もうだめだ。ラスプーチンを首都から追放する勅令は破棄された。しかし、ラスプーチンの身は安全ではなかった。
この告発は明らかにアレクサンドラを悩ませ、彼女はラスプーチンの生涯について独自に調査を行った。彼女は1908年にアルキマンドライト・フェオファンにシベリアを訪れ、証拠を調べるよう依頼した。フェオファンが集めた証拠は、安心させるものであると同時に、不安なものであった。誰もラスプーチンの宗派活動を非難せず、ペーター神父も教会の調査の予想外の結果にショックを受けながらも、ラスプーチンがロシア正教会の敬虔な信者であるように見えるということに同意していた。しかし、フェオファンは、ホストファミリーの家のぎこちない優雅さが気になった。サロフ近郊のディヴィーエフ修道院の修道院長に、この農夫のことを尋ねると、彼女は怒りながら「あなたのラスプーチンにはこうすべきです」と言いながら、フォークを床に投げつけた。
フェオファンの報告はアレクサンドラの疑念を晴らすことができず、彼女は1909年、アンナ・ヴィルボヴァら2人の婦人にポクロフスコエに噂を調査するよう依頼した。”私には探偵の腕前など少しもありません!” ヴィルボヴァは抗議したが、言われたとおりにした。ラスプーチンはペルミで彼らの列車に出会った。彼は女性用コンパートメントに入り、メイドと一緒に上の寝台で一晩を過ごすことにした。若い女性は、グレゴリーが自分をなめていると叫び始め、その晩はずっと廊下にいることになった。ラスプーチンは無実を主張し、女性たちは彼が不適切なことをするのを実際に見ていないことを認めざるを得なかった。
ポクロブスコエのすべてがアンナ・ヴィルボヴァを魅了した。彼女はラスプーチン家の居住区を「まるで聖書のような簡素さ」と賞賛した。食事はレーズン、パン、ナッツ、それにお菓子が少々という質素なものであった。ラスプーチンの友人たちは夜になるとやってきて、讃美歌を歌い、「素朴な信仰と熱意」をもって祈った。
しかし、他の婦人たちの報告は矛盾しており、結論は出ていなかった。ラスプーチンが誘惑しようとしたメイドの女性は、皇后にラスプーチンは危険な淫乱者であると警告した。苛立ったアレクサンドラは、この問題を追及した。彼女はラスプーチンが侍女に手を出すのを目撃したのか?いいえ、その日は夜で、彼女は実は眠っていた。ヴィルボヴァは何もなかったと言い張った。ラスプーチンはまたもや「純真さと聖人ぶり」の犠牲になったのだと、自分は現場にいなかったことを認めざるを得なかったが。アレクサンドラは自分の聞きたいことを聞き、それ以外は無視し、この事件を誤解として片付けた。
アレクサンドラには、自分の意見を通すために、出来事や人を評価する珍しい能力があった。彼女が依頼したポクロブスコエへの訪問は、彼女が不快な事実や自分の直感を無視することができることを示しており、今後の展開を予感させるものであった。アレクサンドラのラスプーチンに対する見方は、癒し手、カウンセラーとしてのラスプーチンに対する信仰と信頼によって形作られた。ニコライは農民にそこまで献身的になることはなかったが、息子を愛する父親として、シベリアの神秘主義者でありヒーラーであるラスプーチンに等しく依存していたのである。ある時、ストリピンがラスプーチンが王位の威信を損ねていると主張したとき、皇帝はこのことをほのめかした。皇帝はついにこう言った「あなたの言うことはすべて真実かもしれない。しかし、ラスプーチンのことは二度と私に話さないように。いずれにせよ、私には何もできない」と言った。この発言は不可解で、ストリピンはほぼ間違いなく誤解した。彼はニコライが妻に立ち向かう強さや勇気がないと認めているのだと思った。しかし、皇帝はアレクシスが血友病であり、ラスプーチンが彼のヒーラーであるという、より重大な事実も考えていたかもしれない。
このため、ラスプーチンを宮廷から追放することはできないが、それを知らない敵は、追放を実現させようとし続けた。1909年、ラスプーチンが彼の初期の熱烈な信奉者の一人であるキオニヤ・ベルラツカヤを強姦したとき、彼らの大義名分はさらに強まった。ベルラツカヤは震え上がり、教会がこの悪党を罰してくれることを願い、フェオファンにこの問題を持ち込んだ。フェオファンは、ラスプーチンの側近からこのような告発を受けるのは初めてだった。フェオファンは敬虔な君主論者であり、最終的にラスプーチンは偽りの霊的指導者であり、王位を破壊する前に止めなければならないと判断した。
嵐が吹き荒れていた。1910年を通じてラスプーチンの証拠が増え続け、彼の淫乱な行動の噂が社会全体に波及していった。フェオファンはベルラツカヤに関するスキャンダラスな情報をモンテネグロ姉妹に伝えたが、今度は姉妹が耳を傾ける用意があった。1908年以降、彼女たちとアレクサンドラとの関係は悪化の一途をたどっていた。最初はアンナ・ヴィルボヴァの問題だった。彼女の重要性が増すにつれ、モンテネグロ姉妹と皇后のそれまでの友好関係が崩れていったのだ。その後、首都で悪い噂が流れ、姉妹はかつての被保護者を疑惑の目で見るようになり、やがて敵対心に変わっていった。ミリツァとアナスタシアはフェオファンとともに、ラスプーチンはロマノフ王朝に危険をもたらす狡猾なペテン師に過ぎないという信念を持った。
1910年の春、ラスプーチンに対する新たな、そしてさらに厄介な告発がアレクサンドル宮殿内部からもたらされた。4人の大公妃の家庭教師であるソフィー・チュチュエバは、ラスプーチンが就寝時に寝間着姿で彼女たちを訪問していると訴えたのだ。しかし、オルガは15歳、タチアナは13歳であり、彼女たちは女性の仲間入りをしていた。チュチュエバは、宮廷はスキャンダルで成り立っているのだから、ゴシップのネタになるようなことをしてはいけないと考えた。ニコライはついに、チュチェヴァの存在が問題になることを悟り、彼女に詰め寄った。「この人を知らないくせに」と叱った。そして、「もし、あなたがこの家にいる人を批判するのなら、世間にではなく、私たちに言うべきだ」と叱った。チュチュエバは反抗的だったので、アレクサンドラは彼女を解雇した。
ラスプーチンはこの時点で、都の多くの女性を恨み、怒らせていた。何人かが前に出て話をした。最初はベルラツカヤ、次にチュチュエバ、そして今度は3人目の女性が声を上げた。ツァレヴィチの乳母であったマリア・ヴィシュネコヴァは、ラスプーチンが宮殿で彼女に性的暴行を加えたと主張した。皇后はそれを信じようとしなかったが、ヴィシュネコヴァはそれを主張し、アレクサンドラは彼女を解雇した。コーカサスのキスロヴォーツクの療養所で療養していたヴィシュネコワは、サンクトペテルブルクの大司教としてロシア正教会で最も権力を持つアンソニーに偶然出会う。ヴィシュネコヴァはアンソニーに、自分の言っていることは真実であり、アレクシスを「悪魔の魔の手」から救わなければならないと説得した。アンソニーはニコライにこの話を持ちかけると、皇帝は宮殿のことはすべて自分の問題だと言い張り、ショックを受けた。アンソニーは動揺し、ロシアの支配者はスキャンダルとは無縁の生活を送るべきだと主張し、皇帝を叱責した。
ミリツァとアナスタシアはフェオファンとともにアレクサンドラに警告したが、アレクサンドラはすべてを拒絶した。皇后はモンテネグロ人に二度とラスプーチンのことを言うなと言い、今後、家族内で彼らの存在を無視するように最善を尽くした。フェオファンはクリミアに移送された。
1910年の初夏、帝国の新聞記者たちは、ラスプーチンの評判を落とそうと、組織的ともいえる行動を開始した。教会観察者であるミハエル・ノヴォセロフはモスクワ新聞に大きな記事を書き、ラスプーチンに “霊的な偽物 “というレッテルを貼った。リベラルな「演説」は、「国家の有力者」と霊的指導者のつながりを調査するよう求めた。検閲官は、ジャーナリストがラスプーチンの名前をロマノフ家の一員と結びつけることを許さなかったが、誰もがそのメッセージを理解した。ニュータイムズ紙は政府の見解を反映することが多く、ラスプーチンを貶めるためにどこまでやるかということを示す人がいるということだけが「ニュース」だと言って、この記事を誇張や嘘だと断じたのである。
なぜラスプーチンはこのような無謀な行動をとったのか。彼は首都にいた最初の2年間は自分自身を制御していた。しかし、次の3年間で何かが変わった。おそらく成功に誘惑されて、もう自分の衝動をコントロールする必要はないと考えたのだろう。ラスプーチンは、自分には霊的な賜物があり、神の使命に召されていると確信していたので、自分自身についてかなり多くのことを弁解することができた。彼の人格の高尚な部分と卑しい部分は常に互いに争っていたが、1908年ごろからバランスが崩れ始めた。
ラスプーチンがそのような態度をとることと、ニコライとアレクサンドラが彼の欠点を無視し、報告を排除し、彼らの見解に異議を唱える人々を罰することは全く別のことであった。人々は、皇帝夫妻は騙されやすい、世間知らずだと結論づけた。しかし、彼らは多くの人が思っている以上に理解していた。オルガは、兄夫婦はラスプーチンの性格を「十分に理解していた」と主張した。「彼らがラスプーチンを悪のできない聖人とみなしていたというのは全くの誤りです」と彼女は数年後に断言した。二人とも「ラスプーチンに騙されたことも、彼について少しも幻想を抱いたこともなかった」のである。
しかし、ラスプーチンがオルガをソファに座らせ、ニコライとアレクサンドラが気まずそうに見守る中、オルガを急に移動させたことがある。それでも二人はラスプーチンの最悪の行動を見たことがない。ラスプーチンが酔っ払って突然ツァールスコエ・セローに現れざるを得なくなったとしても、彼はいつも気を取り直して普通の振る舞いをすることができた。1916年のある時、アレクサンドラは夫に、彼らの友人が「集会での夕食の後、とても陽気だった。しかしほろ酔いではなかった」と報告した。ニコライとアレクサンドラは、最も下品な話を否定しても、ラスプーチンの性格の暗黒面をいくらかは理解していた。
それを知ってどうするのか。息子の命を守ることができる唯一の男を手放すべきか?彼らはラスプーチンを必要としていた。そのためニコライとアレクサンドラは彼の不品行を合理化し、厄介な問題を提起する人々に怒りをぶつけることを余儀なくされた。皇帝は、たとえ証拠が明白であったとしても、些細な誤りを突いてすべての告発を却下し、おなじみの告発をまとめた報告書に対処することがよく知られていた。ニコライは、ラスプーチンの聖人としての地位に疑問を投げかけるような、受け入れたくない事実を無視した。ニコライはある評論家に対して、ラスプーチンは自分の疑念を静め、安らぎを与えてくれたと語ったことがある。ラスプーチンは “純粋な信仰 “の人であった。
リリ・デーンは、皇后の数少ない腹心の部下であり、アレクサンドラと農民の関係について、鋭い指摘をしている。デーンは、皇后がラスプーチンを擁護したのは「彼女と皇帝が彼に友好の手を差し伸べたから」であり、それが間違いであったかもしれないことを認めることができなかったのだと考えた。デーンは、皇后のラスプーチンへの信頼を、ヴィクトリア女王とジョン・ブラウンの関係になぞらえた。両者とも、親友の選択において「指示されることを拒否」し、これらの友人に対する抗議は、あらゆる反対意見を締め出す強硬な態度を生み出すだけであった。
この先、アレクサンドラはラスプーチンの暗い側面に悩まされることになるが、それを認めることはなかった。彼女は実際にラスプーチンを正当化するために「キリストの聖なる愚か者であったロシアの聖人たち」という研究を依頼した。著者はアレクシス・クズネツォフ神父で、彼の研究は最初サンクトペテルブルク神学院の修士論文として却下された。アレクサンドラはそれを出版させた。クズネツォフはまた、ラスプーチンの影響によってモスクワの副司教に昇進したようだ。クズネツォフ自身は驚くほど率直だった。「私はラスプーチンのこと、彼がどう生きているか、何をしているかには関心がない。ラスプーチンがどう生きようが、何をしようが、そんなことはどうでもいい。事実、彼のおかげで、私はモスクワの司教になって、年俸18000ルーブル、諸々の特典付きで暮らしているんだ!
聖なる愚者であったロシアの聖人たちは、「キリストにおける聖なる愚者」、つまり、その時代には奇人、あるいは精神異常者とみなされながらも、教会に受け入れられた男女の伝統について探求している。アレクサンドラは、ラスプーチンを批判していた友人のカルロヴァ伯爵夫人にその本を貸した。カルロヴァは、この本の中で、聖愚者たちの「性的放縦」について詳述している箇所に誰かが下線を引いていることに気がついた。おそらくアレクサンドラは、これでラスプーチンの行動を「見通しよく」理解することを望んだのだろう。また、彼女は友人の評判を挽回したいと思いつつも、そのいかがわしい一面に気づかないわけではなかったことがわかる。アレクサンドラは、聖なる愚者たちが若い頃に罪を犯しても、神に出会ってからは罪のない人生を送ったという事実を無視したのである。ラスプーチンにはそれが当てはまらない。彼は最後まで罪と悔恨を交互に繰り返し、自分の失敗を嘆き、またそれを繰り返した。このことがラスプーチンを人間らしくしているのだが、アレクサンドラがラスプーチンと似たような人生を歩んでいると感じた男女からラスプーチンを引き離すことにもなった。
ラスプーチンはアレクサンドラにとって重要な存在だったが、彼女の賞賛は常に補強されなければならなかった。そのためには、通常、喜んで提供する人からの賞賛と、息子の再度の治療、そして彼自身との数回の面会が必要だった。そのため、彼女は友人の人生の過酷な現実を見過ごすことができなかった。「彼女はリリ・デーンにこう言った。「主は、ユダヤ人社会で生まれた人たちを信奉者に選ばれたのではありません」。彼女はラスプーチンを旧約聖書の預言者になぞらえた。真理と神聖さを証しするために神によって遣わされたのだと。
つづきを読む ラスプーチンとはどんな人?『ラスプーチン知られざる物語』7
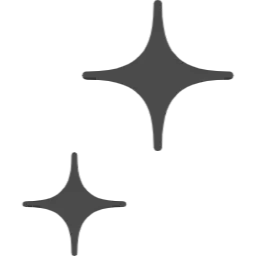
アクセス・バーズはどこから来ているのか?アクセス・コンシャスネスの教えはいったいどこから?
そういった疑問には、やはりこの人【ラスプーチン】を知らなくては始まりません。
ということで、Rasputin Untold Story by Joseph T. Fuhrmann ジョセフ・T・フールマン『ラスプーチン知られざる物語』を読みこもうという試みです。

